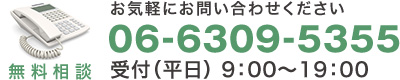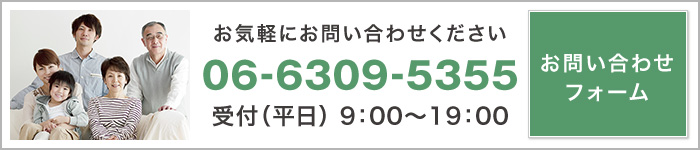家族信託をひと言で言いますと、「信頼できる家族に自分の財産の管理・処分を任せる(託す)」制度です。
家族信託をひと言で言いますと、「信頼できる家族に自分の財産の管理・処分を任せる(託す)」制度です。
この家族信託は、これまでの法制度(成年後見制度、遺言など)ではできなかったことが、できるようになりました。
最大の特徴は次の2つです。
1.財産管理の点から言えば、成年後見制度とは、次元の違う活用ができる。
成年後見(法定後見)は認知症を発症した後に利用する制度ですが、この制度では、本人の財産は、本人のために必要最低限の範囲でしか使用できません。
しかし、家族信託では、本人のために、積極的に財産の運用や処分などをすることが可能となります。
例えば、本人所有の古いアパートの建替え・売却による金銭化、相続税対策のため現金で収益不動産を購入し資産の圧縮(現金と不動産が同じ額であれば、不動産の方が財産の評価が低くなること)することなどは、成年後見では事実上不可能ですが、家族信託では可能になります。
2.相続による財産承継の点から言っても、遺言とは、次元の違う活用ができる。
遺言で行う財産承継は、一代限りで、財産を「誰に」、「何を」渡すかのみを決めることができます。
しかし、家族信託で行う財産承継は、財産を「誰に」、「何を」渡すかのみを決めるだけでなく、渡した財産の管理方法まで指定できます。さらに、一代に限らず、将来を見越して、その次の世代以降の引継先も指定することもできるようになります。
以上の2つの大きな特徴がありますが、家族信託をよく利用されることが多いのは、財産管理のうち認知症対策の場合です。
例えば、預金や不動産を所有している親が認知症を発症されると、それらの財産が凍結してしまいます。財産が凍結してしまうと、預金の引き出しや不動産の購入・売却などができなくなり、財産を何も動かせない状態になるおそれがあります。この時点になると、あとは成年後見制度しか選択肢がなくなり、成年後見開始後は、必要最低限でしか財産の使用ができなくなります。
このような事態を避けるためには、あらかじめ家族信託を活用して、親の所有財産を子に託しておきます。
こうしておけば、子に財産の管理・処分をする権限が移りますので、もし親が認知症を発症されても財産が凍結せずに、子が家族信託の内容に基づいて、親の所有していた財産を管理・処分することが可能となります。
ここでの登場人物の呼び方は、以下のとおりです(家族信託には他にも登場人物や用語が出てくることがありますが、この事例では、シンプルにしています)。
- 財産を託す親(元々の所有者)
「委託」者(いたくしゃ) - 財産を託される子(管理・処分ができる人)
「受託」者(じゅたくしゃ) - 財産の管理・処分の利益を受ける人(親)
「受益」者(じゅえきしゃ)
このように決めておくと、受益者である親は引き続き、財産の管理・処分の利益を受けられるので、結果として、普段の生活状況が変わることはありません。
例えば、託しておく財産を自宅とアパートとした場合は、今までどおり、受益者である父は自宅に住めるし、アパートからの家賃収入も得られることになります。そして、その後に親が認知症になった場合に家族信託の本領が発揮されることになり、資産は凍結せずに、引き続き、子である受託者が財産の管理・処分を続けることができます。
この事例では、①委託者と③受益者を同じ人(親)とし、②受託者を子としたので、登場人物は2人としました。この登場人物が2人のメリットは、名義は形式上、受託者である子に移りますが、経済的価値(自宅に住む権利やアパートの家賃をもらう権利など)は、父のままなので、財産の移動とみなされないことから、贈与税の問題が発生しないことが大きいところです。
次に、①~③を全て別の人にして、登場人物を3人とすることも可能です。
例えば、両親は健在ですが、母の方が認知症を発症している場合、①委託者(父)・②受託者(子)・③受益者(母)として、母に財産の利益(例えば、父のアパートの家賃収入など)を受けさせたい場合です。ある意味、母のために子に財産管理を任せるという理想的な手法なのですが、税金の面から言いますと、経済的価値(この場合アパートの権利と家賃収入)が父から母に移動するため、贈与があったものとみなされ、課税の問題が発生します。そのため、この委託者と受益者が違う手法は税理士などの専門家に相談の上、慎重に行うことが大事です。
次のページから、より具体的に家族信託の活用方法などを解説します。
→「家族信託の種類」